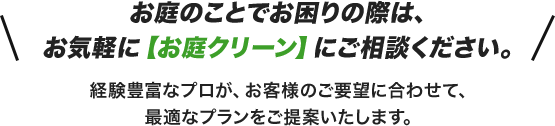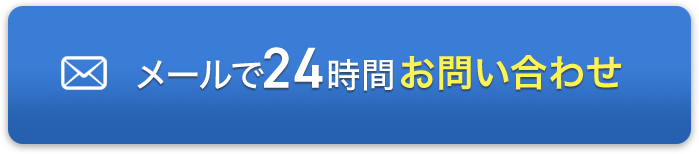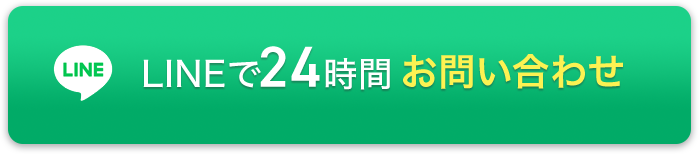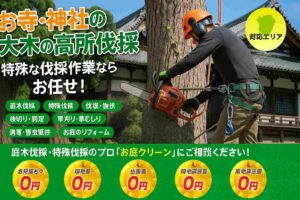プロが教える基本の切り方と道具選び

「庭の木が伸び放題で、どうにかしたいな…」 「自分で剪定してみたいけど、どこから手をつけていいか分からない…」
こんにちは!「お庭クリーン」の植木職人です。 ガーデニングを始めたばかりの方にとって、庭木の剪定は少しハードルが高く感じられるかもしれませんね。しかし、基本的な知識さえあれば、ご自身の庭を美しく、健やかに保つことができます。
この記事では、プロの視点から、初心者の方が「これだけは知っておきたい!」という剪定の基本を、道具選びから具体的な切り方、安全のポイントまで、分かりやすく解説していきます。さあ、一緒に剪定の第一歩を踏み出してみましょう!
1. はじめに:なぜ剪定が必要なの?

そもそも、なぜ庭木は剪定が必要なのでしょうか?
剪定をしないまま木が伸びていくと、見た目が悪くなるだけでなく、様々な問題が起こります。
- 景観の悪化: 枝が混み合い、ボサボサの印象になってしまいます。
- 病害虫の発生: 風通しや日当たりが悪くなり、ジメジメした環境を好む病気や害虫が発生しやすくなります。
- 木の健康被害: 内部の枝まで日光が届かず、木全体が弱ってしまいます。
- ご近所トラブル: 伸びた枝が隣家や道路にはみ出し、トラブルの原因になることも。
適切な時期に正しい方法で剪定を行うことで、これらの問題を解決し、たくさんのメリットが生まれます。
- 美しい見た目をキープ: 木の形が整い、お庭全体がスッキリと美しい印象になります。
- 健康な成長をサポート: 風通しと日当たりが良くなり、木が元気に育ちます。
- 花や実つきが良くなる: 栄養が効率よく行き渡り、翌年の花や実を楽しむことができます。
剪定は、いわば庭木の「健康診断」であり「ヘアカット」。少し手をかけてあげるだけで、庭木は生き生きと応えてくれますよ。
2. まずは揃えたい!剪定の基本道具3選

「いざ剪定!」と思っても、道具がなければ始まりません。まずは、これだけは揃えておきたい基本の道具を3つご紹介します。
① 剪定バサミ
- 用途: 人の指くらいの太さ(直径1.5cm程度)までの、比較的細い生木を切るのに使います。庭木剪定の基本となる、最も使用頻度の高いハサミです。
- 選び方のポイント: 自分の手の大きさにフィットするものを選びましょう。グリップの大きさやバネの硬さなど、実際に握ってみてしっくりくるものが一番です。切れ味の良いものを選ぶと、少ない力でスパッと切れるため、木への負担も少なく、作業も楽になります。
- こういう作業に便利!: バラやアジサイなど、低木の細かい枝を整理する作業に最適です。
② 植木バサミ

- 用途: 葉を刈り込んだり、細い枝を整えたり、形をデザインするのに使います。ツツジやサツキなどを丸い形に整える「玉散らし」のような作業で活躍します。
- 選び方のポイント: 刃が長く、細いのが特徴です。こちらも、持った時のバランスや重さが自分に合っているかを確認しましょう。
- こういう作業に便利!: 生垣の表面をきれいに刈り揃えたり、松の葉を整えたりする繊細な作業に向いています。
③ 剪定ノコギリ

- 用途: 剪定バサミでは切れない太い枝(直径2cm以上)を切る時に使います。
- 選び方のポイント: 刃の長さに種類がありますが、家庭用なら20~25cm程度のものが使いやすいでしょう。持ち運びや収納に便利な「折りたたみ式」も人気です。
- こういう作業に便利!: 少し大きくなった木の、不要な太い枝を根元から切り落とす時に頼りになります。
3. これだけは覚えたい!基本の切り方「3つのカット」
道具が揃ったら、いよいよ実践です。まずは、全ての剪定の基本となる「3つのカット」を覚えましょう。
① 透かし剪定
木の内部まで風と光を通すための、最も基本的な剪定方法です。
- 目的: 枝の混み合っている部分を間引くことで、風通しと日当たりを良くします。病害虫の予防になり、木が健康に育ちます。
- 切り方: 不要な枝を、枝分かれしている付け根から切り取ります。枝の途中で切ると、そこから新しい枝がたくさん出てきて余計に混み合ってしまうので注意しましょう。
- (イメージ図:一本の太い枝から数本の枝が出ている。そのうちの一本が、他の枝と交差するように伸びている。その交差している枝の、根元にハサミを当てて切るイラスト)
② 切り戻し剪定
伸びすぎた枝を短くして、木の大きさをコントロールする剪定方法です。
- 目的: 木全体の大きさをコンパクトに整えたり、枝の先に栄養を集中させて花つきを良くしたりします。
- 切り方: 枝の途中で切りますが、切る位置が重要です。**枝にある芽(新しい葉や枝が出てくる膨らみ)の、少し上(5mm~1cm程度)**で切ります。芽の向きを確認し、外側に向いている芽の上で切るのがポイントです。そうすることで、新しい枝が木の内側ではなく外側に向かって伸び、きれいな樹形になります。
- (イメージ図:一本の枝に、複数の芽が付いている。外側を向いている芽の、少し上で斜めに切っているイラスト)
③ 枯れ枝・不要枝の除去
木の健康を保つために、不要な枝を取り除きます。
- 見分け方:
- 枯れ枝: 葉がなく、樹皮がポロポロと剥がれたり、色が変色したりしている枝。
- 不要枝: 他の枝の成長を邪魔するような枝のこと。
- 交差枝: 他の枝とクロスしている枝。
- 平行枝: 近くで同じ方向に伸びている枝。
- 逆さ枝: 本来伸びるべき方向とは逆に、幹に向かって伸びている枝。
- 切り方: 基本的には「透かし剪定」と同じで、枝の付け根から切り取ります。枯れ枝は見た目が悪いだけでなく、病害虫の温床になる可能性もあるため、見つけ次第取り除きましょう。
4. いつ切るのがベスト?剪定の時期
「剪定はいつやってもいいの?」という質問もよくいただきます。実は、剪定には適した時期があります。大きく分けて2つのシーズンを覚えておきましょう。
- 冬期剪定(基本剪定): 木の成長が止まる12月~2月頃に行います。葉が落ちている落葉樹は骨格がよく見えるため、樹形を整える「透かし剪定」や「切り戻し剪定」に最適な時期です。この時期の剪定は、木への負担が少ないのがメリットです。
- 夏期剪定(軽剪定): 木の成長が活発な7月~9月頃に行います。伸びすぎた枝や混み合った部分を軽く整える「透かし剪定」が中心です。強く切りすぎると木が弱ってしまうので、あくまでも軽めに行うのがポイントです。
常緑樹と落葉樹の剪定時期
- 常緑樹(シマトネリコ、オリーブ、キンモクセイなど): 比較的暖かい時期の3月~6月頃が主な剪定時期です。真夏や真冬は木が弱りやすいので避けましょう。
- 落葉樹(ハナミズキ、モミジ、アオダモなど): 葉が落ちて休眠期に入る11月~2月頃が最適です。
【注意!】花木の剪定時期 ツツジやサツキ、アジサイなどの花木は、剪定時期を間違えると翌年花が咲かなくなってしまいます。基本的には**「花が終わった直後」**に剪定すると覚えておきましょう。
5. 安全に作業するための注意点
楽しく安全に作業するために、以下の点は必ず守ってください。
- 服装: 長袖・長ズボンで肌の露出を避け、虫刺されや枝による怪我を防ぎましょう。滑り止めのついた手袋、頭を守る帽子も忘れずに。
- 脚立: 脚立を使う際は、必ず平らで安定した場所に設置してください。脚立の上で無理な体勢をとったり、手を伸ばしすぎたりするのは絶対にやめましょう。転落事故につながる大変危険な行為です。
- 天候: 雨の日やその翌日は、枝や足元が滑りやすく危険です。また、風の強い日も枝が揺れて作業がしにくいため、避けるようにしましょう。
6. まとめ:自分でできる範囲とプロに任せる判断基準
ここまで、ご自身で剪定を行うための基本をご紹介しました。 まずは、ご自身の背丈くらいの低い木や、手の届く範囲の細い枝から挑戦してみてはいかがでしょうか。「透かし剪定」で不要な枝を1~2本切るだけでも、木はスッキリしますし、達成感も得られるはずです。
しかし、中にはプロに任せた方が良いケースもあります。
- 高すぎる木(脚立を使っても届かないなど)
- 剪定ノコギリでも切れないような太い枝の伐採
- 毛虫などの害虫が大量に発生している場合
- ご自身での作業に少しでも不安や恐怖を感じる場合
このような場合は、無理をしないでください。高所からの転落や、チェーンソーなどの専門工具による怪我は、命に関わることもあります。
木にとっても、ご自身にとっても、安全で確実な方法を選ぶことが最善の選択です。
「お庭クリーン」では、庭木1本からの剪定も喜んで承っております。どの枝を切ればいいか分からない、高くて自分ではできないなど、剪定に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富なプロが、あなたの大切な庭木を美しく、健やかに整えます。
関連ページ
- 他社で断られた高木・難所の伐採もお任せください|特殊伐採の専門技術
- 【木の幹が1m超え】の伐採作業なら安心信頼のお庭クリーンにお任せください!
- 【台風・災害時の倒木】放置は危険!自分でできる処理方法と業者依頼の判断基準
- 火災保険の申請方法を徹底解説!請求の流れと必要書類とは
- 雑草対策の決定版!もう草むしりで悩みたくないあなたへ
対応エリア
対応エリア
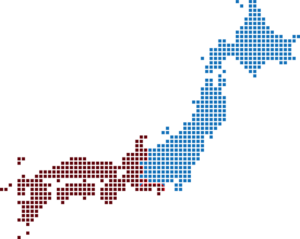
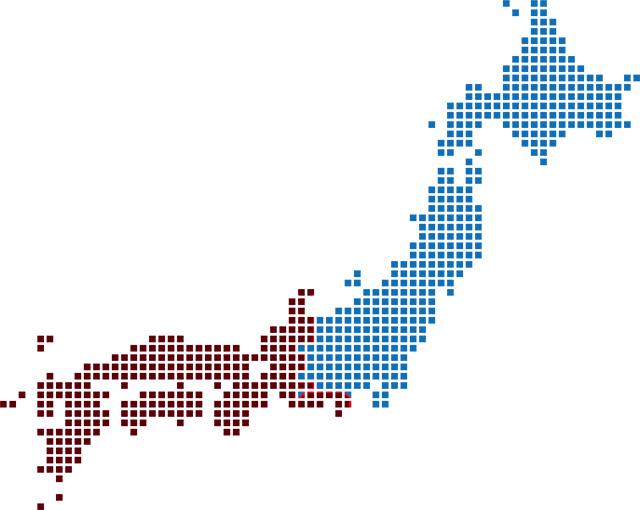
※その他エリアもご相談ください。