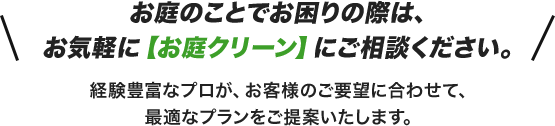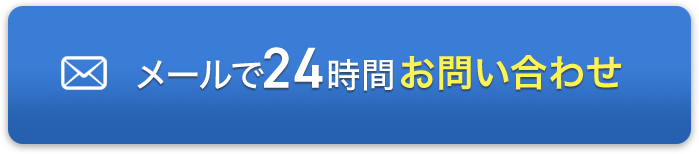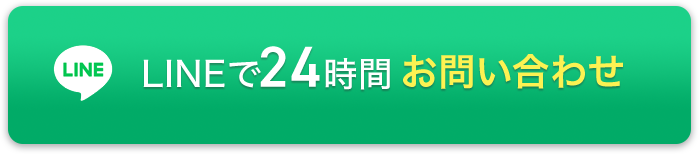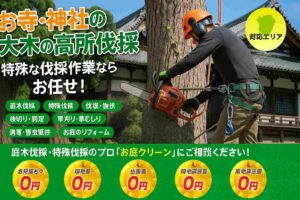庭木伐採で近隣トラブル!回避策と解決方法を専門家が解説!
この記事では、庭木伐採で起こりがちなリアルなトラブル事例から、それを未然に防ぐための具体的な対策、そして万が一トラブルになってしまった場合の解決方法まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。
伐採業者をお探し、 【危険を伴う専門的な技術が必要な作業】お役立ち情報になれば幸いです。
こんなことで揉めるの?庭木伐採トラブルのリアルな実例

庭木の伐採は、単に「木を切る」という作業ではありません。そこには、ご近所さんの生活や想い、地域の景観など、様々な要素が複雑に絡み合っています。ここでは、実際にどのようなトラブルが起こりうるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
事例1:お隣さんの枝、勝手に切っていい?「越境トラブル」

これは最も多いトラブルの一つです。自分の敷地に伸びてきた隣の家の枝葉、気になりますよね。
- 「邪魔だから」と、お隣さんに無断で枝を切ってしまった。
- 「枝を切ってください」とお願いしても、なかなか対応してくれない。
- 伐採のやり方や切る範囲で意見が対立し、話がこじれてしまった。
「自分の敷地に入ってきたんだから、切ってもいいでしょ?」と思うかもしれませんが、法律(民法)では、枝は木の所有者のものです。勝手に切ってしまうと、逆にこちらが「器物損壊」で訴えられる可能性もゼロではありません。たかが枝、されど枝。所有権が絡むデリケートな問題なのです。
(※2023年4月の民法改正で、一定の条件下では自分で切れるようになりました。詳しくは後述します。)
事例2:休日の朝に鳴り響くチェーンソー音!「騒音トラブル」

庭木の伐採には、チェーンソーや重機など、大きな音が出る機械がつきものです。自分にとっては数時間の作業でも、ご近所さんにとっては平穏な日常を壊される迷惑行為になりかねません。
- 「せっかくの休みなのに、朝早くからうるさくて眠れなかった!」と苦情が来た。
- 赤ちゃんのいるお宅や、在宅勤務中のご近所さんから「集中できない」とクレームが入った。
- 連日の騒音で、ご近所さんが精神的なストレスを感じてしまった。
特に、住宅が密集している地域では、音の問題は非常に深刻です。「お互い様」で済まないケースも多く、作業の時間帯や期間への配慮が欠けていると、一気に関係が悪化してしまいます。
事例3:木がなくなったら丸見えに!「日照・プライバシーのトラブル」

長年、目隠しや日よけの役割を果たしてくれていた大きな木。それを伐採することで、周辺の環境がガラリと変わってしまうことがあります。
- 「木のおかげで夏は涼しかったのに、伐採後は日差しが強すぎて家にいられない!」
- 「お宅の木を目隠しにしていたのに、リビングが丸見えになってプライバシーがなくなった!」
- 隣の家の家庭菜園やガーデニングに、日当たりが変わりすぎて悪影響が出てしまった。
伐採する側にとっては「スッキリして明るくなった!」と感じても、お隣さんにとっては「大切なものが奪われた」という喪失感につながることも。長年その環境に慣れ親しんできた人ほど、変化に対するストレスは大きいものです。
事例4:街のシンボルだったのに…「景観トラブル」

特に立派な大木や、美しい花を咲かせる桜の木などは、個人の所有物であると同時に、地域の景観を構成する大切な要素になっていることがあります。
- 「あの桜を見るのが毎年の楽しみだったのに…」と、近隣住民から落胆の声が上がった。
- 「地域の景観を損なう」として、町内会で問題になった。
- 鳥の巣があった木を切ったことで、「生態系を破壊するのか」と非難された。
自分にとってはただの庭木でも、地域の人々にとっては「思い出の木」「シンボツリー」である可能性も。そうした場合、伐採に対する反発は予想以上に大きくなることがあります。
事例5:この費用、どっちが払うの?「費用負担トラブル」

越境した枝の伐採など、複数の家に関わる作業の場合、その費用を誰が負担するのかで揉めることがあります。
- 「そっちの家の木なんだから、費用は全部持ってよ」
- 「いやいや、そっちが切れって言ったんだから、折半でしょ」
- 伐採後の枝葉の処分費用まで含めるかで、話がまとまらない。
お金が絡むと、どうしても話はシビアになりがちです。事前に誰が何をいくら負担するのか、明確な取り決めがないと、後々まで続くしこりを残す原因になります。
事例6:切った後も問題が?「根っこのトラブル」

木は、地上に見える部分だけでなく、地中にも大きく根を張っています。伐採後、この「根」が新たなトラブルの火種になることもあります。
- 隣の敷地まで伸びた根っこをどう処理するかで揉めた。
- 太い根が腐って、地面が陥没しないか心配されている。
- 根を完全に撤去(抜根)するための追加費用で、トラブルが再燃した。
特に大木の場合、根の処理は伐採以上に手間と費用がかかることがあります。「木を切れば終わり」ではないことを、頭に入れておく必要があります。
トラブルを未然に防ぐ!伐採前にやるべき5つのこと

ここまで読むと、「庭木伐採って、なんて大変なんだ…」と気が重くなってしまったかもしれません。しかし、ご安心ください。これからお伝えする「5つの事前対策」を丁寧に行うことで、トラブルのリスクは劇的に減らせます。
1. 何よりも大切!「ご近所への事前相談」という思いやり

トラブルの9割はコミュニケーション不足が原因です。伐採を決めたら、まず最初にご近所へ相談に伺いましょう。一方的な「報告」ではなく、「相談」という姿勢が何よりも大切です。
伝えるべき内容と伝え方のコツ
- なぜ伐採するのか?(理由): 「木が大きくなりすぎて、台風の時に倒れないか心配で…」「日当たりが悪く、家の中が暗くなってしまったので…」など、正直な理由を伝えましょう。あなたの悩みを共有することで、相手も理解しやすくなります。
- いつ、どのくらいの時間やるのか?(日時・期間): 具体的な予定日と、作業にかかるおおよその時間を伝えます。「〇月〇日の午前9時から3時間ほど、作業をさせていただく予定です」のように明確に。
- どんな影響があるか?(騒音・ホコリなど): 「チェーンソーを使うので、少し大きな音が出てしまいます」「ホコリが舞うかもしれないので、お洗濯物など気をつけていただけると助かります」と、想定される迷惑を正直に伝え、お詫びの言葉を添えましょう。
- 相手の都合を聞く: 「ご迷惑をおかけしますが、ご都合の悪い日などありますでしょうか?」と、相手の意見を聞く姿勢を見せることが、信頼関係を築く上で非常に重要です。
可能であれば、両隣と裏のお宅、そして作業車両の出入りで影響がありそうなお宅には、一週間前までに直接ご挨拶に伺うのが理想です。菓子折りなどを持参すると、より丁寧な印象になります。
2. ここは誰の土地?「境界線の確認」は慎重に

「だいたいこの辺が境界線だろう」という曖昧な認識は、後々の大きなトラブルの元です。特に、境界線ギリギリに生えている木を伐採する場合は、必ず事前に境界線を明確にしておきましょう。
境界線を確認する方法
- 公的な書類をチェック: 法務局で取得できる「登記簿謄本」「公図」「地積測量図」などで、土地の正確な情報を確認します。
- 境界杭を探す: 敷地内にあるコンクリートや金属の「境界杭」を探しましょう。見つからない、または位置がよく分からない場合は、安易に判断せず、専門家(土地家屋調査士など)に相談することをおすすめします。
- お隣さんと一緒に立ち会い確認: 最も確実なのは、お隣の所有者の方と一緒に現地で境界線を確認することです。「この杭で間違いないですよね?」と双方で認識を合わせ、可能であればその内容を簡単なメモや合意書として残しておくと万全です。
3. プロに任せる安心感!「信頼できる伐採業者の選び方」

費用を抑えようとDIYで…と考える方もいるかもしれませんが、高所での作業やチェーンソーの扱いは非常に危険です。安全面、そしてご近所への配慮の面からも、専門の伐採業者に依頼するのが最善の選択です。ただし、業者なら誰でも良いというわけではありません。
信頼できる業者のチェックポイント
- 実績と経験は十分か?: ホームページで施工事例を確認したり、創業年数を見たりして、経験が豊富かチェックしましょう。
- 「損害賠償保険」に加入しているか?: 万が一、作業中にお隣の家の壁を傷つけたり、車を破損させたりした場合に備え、保険に加入しているかは必ず確認してください。
- 見積もりは明確か?: 「伐採一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりを出す業者は要注意です。「どの木をどう切るのか」「伐採後の処分費用は含まれているか」「重機代は別途か」など、作業内容と費用の内訳が詳細に記載されているか確認しましょう。複数の業者から相見積もりを取るのが基本です。
- 近隣への配慮をしてくれるか?: 「作業前に近隣への挨拶回りも行います」「養生をしっかりして、ホコリや枝が飛ばないように配慮します」など、近隣への気配りができる業者を選びましょう。
4. 安全第一!「作業前の安全確認と準備」
業者に依頼する場合でも、依頼主として安全確認のポイントを知っておくことは重要です。思わぬ事故を防ぎ、スムーズな作業につながります。
確認・準備すべきこと
- 周辺環境のチェック: 木の周りに電線や電話線はないか?すぐ近くにカーポートや物置などはないか?伐採した木が倒れる方向に人や物がないか、業者と一緒に最終確認しましょう。
- 必要な許可は取れているか?: 自治体によっては、地域の景観を守るために「保存樹木」に指定されている木があります。こうした木を伐採するには、役所の許可が必要です。事前に自分の家の木が該当しないか、市役所や区役所の緑地管理担当課などに確認しておくと安心です。
- 作業スペースの確保: 作業当日は、職人さんやトラックがスムーズに出入りできるよう、駐車スペースを確保したり、周辺の物を片付けたりしておきましょう。
5. 後片付けまでが伐採作業!「伐採後の処理と環境への配慮」

木を切り倒して「はい、おしまい」ではありません。その後の対応が、ご近所との将来的な関係を左右します。
- 伐採木の適切な処分: 切った枝や幹は、法律(廃棄物処理法)に基づき、適切に処分しなければなりません。通常は伐採業者が処分まで請け負ってくれますが、見積もりに処分費用が含まれているか必ず確認しましょう。
- 跡地の整備: 根っこが残っていると、つまづいたり、シロアリの温床になったりすることがあります。必要であれば、根を取り除く「抜根(ばっこん)」作業も検討しましょう。地面を平らにならし、きれいな状態に戻すことで、ご近所にも良い印象を与えます。
- 代替の植栽を検討する: 大きな木を伐採して景観が変わってしまった場合、代わりに低木や花などを植えることで、環境への配慮を示すことができます。「木がなくなって寂しくなりましたが、今度はきれいな花を植えようと思います」と一言添えるだけで、ご近所さんの受け止め方も変わってくるはずです。
もしトラブルになってしまったら?段階別・解決へのロードマップ

どんなに気をつけていても、人間関係にはすれ違いがつきものです。万が一、ご近所さんとトラブルになってしまった場合でも、慌てず冷静に対処することが大切です。感情的にならず、以下のステップで解決の道を探りましょう。
STEP 1:基本の「き」【当事者間での話し合い】
まずは、当事者同士で冷静に話し合うことから始めます。こじれてしまった関係を修復するための、最も重要で基本的なステップです。
話し合いを成功させるポイント
- 相手の話を最後まで聞く: 途中で口を挟まず、「あなたはそう感じていたのですね」と、まずは相手の主張や感情をすべて受け止める姿勢を見せましょう。
- 感情的にならない: 「なんでそんなこと言うんだ!」とカッとなると、話は進みません。深呼吸をして、客観的な事実(いつ、何が、どうなったか)に基づいて話を進めることを意識してください。
- 自分の非は認める: もし自分に配慮が足りなかった点があれば、「〇〇の点でご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした」と素直に謝罪しましょう。
- 妥協点を探る: 100%自分の主張を通そうとせず、「では、このようにするのはいかがでしょうか?」と代替案や妥協点を探る努力をすることが、解決への近道です。
話し合いが難しい場合は、信頼できる町内会長や、共通の知人など、中立的な第三者に間に入ってもらうのも一つの手です。
STEP 2:専門家の知恵を借りる【弁護士への相談】
当事者間の話し合いではラチが明かない。相手が感情的で話にならない。そんな時は、法律の専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。
「弁護士なんて、大げさな…」と感じるかもしれませんが、これは裁判を起こすためだけではありません。むしろ、裁判を避けるために弁護士に相談するのです。
弁護士に相談するメリット
- 法的な状況が整理できる: 自分の主張が法的に正しいのか、相手の要求は正当なのかを客観的に判断してもらえます。
- 最適な交渉方法を教えてもらえる: 専門家の視点から、どうすれば穏便に交渉を進められるか、具体的なアドバイスがもらえます。
- 相手への「本気度」が伝わる: 弁護士が代理人として内容証明郵便を送るなどするだけで、相手の態度が軟化し、話し合いに応じるケースも少なくありません。
多くの法律事務所では「初回相談30分~1時間無料」といったサービスを行っています。まずはそうした制度を利用して、気軽に相談してみることをお勧めします。
STEP 3:中立な第三者を交える【民事調停】
弁護士を介した交渉でも解決しない場合、裁判所の手続きを利用する方法があります。しかし、いきなり「訴訟(裁判)」ではなく、その前段階として「民事調停」という穏やかな手続きがあります。
調停とは、裁判官と民間の有識者からなる「調停委員」が中立な立場で間に入り、双方の言い分を聞きながら、話し合いによる合意(和解)を目指す制度です。
調停のメリット
- 費用が安い: 訴訟に比べて、手数料(申立費用)が数千円程度と安価です。
- 手続きが簡単: 弁護士に依頼せず、自分で行うことも可能です。
- 非公開で行われる: 話し合いは非公開の部屋で行われるため、プライバシーが守られます。
- 柔軟な解決が可能: 法律で白黒つけるだけでなく、実情に合った柔軟な解決策を探ることができます。
調停で合意した内容は、判決と同じ法的効力(債務名義)を持ちます。
STEP 4:最後の手段【訴訟(裁判)】
調停でも合意に至らない、あるいは相手が話し合いに一切応じない。そうした場合には、最終手段として「訴訟」を提起することになります。
訴訟は、裁判官が法に基づいて「どちらが正しいか」を判断し、判決を下す手続きです。白黒ハッキリさせることができますが、多くのデメリットも伴います。
- 時間と費用がかかる: 解決までに1年以上かかることも珍しくなく、弁護士費用も高額になります。
- 精神的な負担が大きい: 相手と法廷で争うことは、大きなストレスを伴います。
- ご近所関係は完全に破綻する: 裁判で勝ったとしても、その後のご近所付き合いは絶望的になると覚悟する必要があります。
訴訟は、あくまで「最後の砦」です。本当にそれ以外の解決方法がないのか、弁護士と十分に相談し、慎重に検討することが重要です。
これだけは知っておきたい!庭木伐採に関わる法律のキホン

トラブルを回避・解決するためには、最低限の法律知識を持っておくことがあなたの身を守ります。ここでは、特に重要な法律を分かりやすく解説します。
民法:ご近所トラブルの基本ルール
【重要】2023年4月1日、民法が変わりました!
長年、ご近所トラブルの種だった「越境した枝」のルールが、2023年4月1日の民法改正で大きく変わりました。
- 【改正前】: 隣の家の枝が越境してきても、勝手に切ることはできず、木の所有者にお願いするしかありませんでした。
- 【改正後(新ルール)】: 原則はこれまで通り「所有者にお願いする」ですが、以下の3つのケースに限り、自分で枝を切り取ることができるようになりました。
- 木の所有者に「枝を切ってください」とお願いしたのに、相当の期間(一般的に2週間程度)内に切ってくれない場合。
- 木の所有者が誰なのか分からない、またはどこにいるか不明な場合。
- 台風で枝が折れかかっていて、今にも隣家に被害を及ぼしそうな「急迫の事情」がある場合。
この改正により、泣き寝入りするしかなかったケースでも、法的な対抗手段が取りやすくなりました。ただし、だからといって無断で切って良いわけではないので、まずは所有者にお願いするという手順を踏むことが大前提です。
根っこは昔から自分で切れる!
枝とは違い、越境してきた「根」については、昔から土地の所有者が自分で切り取って良いとされています(民法第233条)。
土地の所有権は空と地面にも及ぶ
「土地の所有権は、法令の制限内でその土地の上下に及ぶ」(民法第207条)と定められています。つまり、自分の土地の上空や地下も自分のもの。だからこそ、自分の土地にある木は自由に伐採できるし、越境してきた根も切ることができるのです。
その他の関連法規
- 騒音規制法: チェーンソーなどの作業は「特定建設作業」に該当する場合があり、作業時間や曜日、音の大きさが規制されていることがあります。作業前に自治体の環境課などに確認しておくと安心です。
- 自治体の条例(保存樹木など): 地域によっては、貴重な樹木を「保存樹木」「保護樹木」として指定している場合があります。これらの木を伐採するには自治体の許可が必要になるため、必ず事前に確認しましょう。
法律は、あなたを縛るものではなく、あなたとご近所の権利を守り、公平な解決を導くためのツールです。正しい知識を持つことが、不要なトラブルを避ける一番の武器になります。
まとめ:大切なのは法律よりも「お互い様」の心
この記事では、庭木伐採に伴う近隣トラブルのリアルな事例から、その回避策、そして解決方法までを詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- トラブルの多くは「越境」「騒音」「日照・プライバシー」などが原因。
- 回避策のキモは「ご近所への事前相談」。誠実なコミュニケーションが何より大切。
- 「境界線の確認」「信頼できる業者の選定」もトラブル防止に不可欠。
- 万が一トラブルになったら、「話し合い → 弁護士相談 → 調停 → 訴訟」の順で冷静に対処。
- 2023年の民法改正で、越境した枝のルールが変わったことを知っておく。
たくさんの対策や法律についてお話ししましたが、最も大切なことはたった一つです。それは、「お互い様」という気持ちと、ご近所への「思いやり」です。
法律で白黒つける前に、まずはお隣さんの立場になって考えてみる。自分の都合だけでなく、相手の生活にも配慮する。その少しの心遣いがあるだけで、防げるトラブルはたくさんあります。
庭木をスッキリさせて、お庭もご近所関係も、より良いものにしていきましょう。この記事が、あなたのその第一歩を、力強く後押しできれば幸いです。
庭木伐採で近隣トラブル!回避策と解決方法を専門家が解説。
伐採で困った?、 【どうすればいいのか?を知りたい】そんなお悩みを解決する!お役立ち・頼りになる・伐採業者としてご利用いただければ幸いです。仙台市の木の伐採業者・お庭クリーン | 高所伐採・抜根